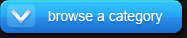雨氷の不思議

「無我の境地」という言葉がある。
剣豪や武道の達人が修行の末に辿り着く究極の精神状態などと想像してみるが、写真に置き換えて考えてみると「無我夢中で撮る」という時が、かなりこの境地に近いのではないだろうか。
瓊末なことに囚われず、自然に、のびのびと被写体と一体になって遊ぶ。きっと、こういうときは構図や露出補正といった、普段あれこれと考え悩む問題も気にならず、一心にその美しさ、素晴らしさ、時には不思議さに全身で感動している。この上ない幸福な時だ。忘れられない一日がある。
2004年3月20日。無我夢中で撮り尽くした一日だった。松本フォトアカデミーの仲間たちと美ヶ原に行った時のことだ。メンバーは5人。走り慣れた林道を、まだ暗いうちに登った。前夜までの雨が上がり、冴え冴えと星が輝いていた。やがて東の空か白み始め、昼夜交代のドラマが進行していった。数えきれないほど、このようなシーンに立ち会ってきたが、この日の朝焼けは格別だった。
北アルプス上空のピンク色の帯が次第に下降して稜線に近づく。星の撮影位置からの移動に手間取り、ハァハァゼェゼェとアルプスの撮影ポイントの丘に登り着いた直後、御来光が3000mの頂に射した。
前夜の雨で、空中が澄んだためか、北アルプスの白き峰々は目の覚める朝焼けに染まった。「間に合ったな」と一息ついて振り返った。閃光に射られるような強烈な光。目の前一面に、キラキラした光の世界が広がっていた。
雨氷だ!一晩のうちに、雨雫が凍ったのだ。足元の一本一本の枯草たちが、アイスキャンディのように見える。コナシの枝もカラマツ林も、すべてが氷の衣を着て、逆光の中に煌いている。標高2000m近い高原では、春先、雨の直後に冷え込むと、この雨氷が出現することがある。これは稀なことで、冬から春への季節変化の中で、気温や風などの微妙な条件が揃わないとなかなか見ることはできない。
10年以上前の話だが、自宅前の川の中で、真冬の月夜に川面が凍りついていく場面を撮影したことがある。月が映る川面を2時間ほど見続けていると、すでにできた薄氷の輪郭部分に向かって、こまかな細い(味の素のような)物体が、スーツ、スーツと水面を滑るように移動してくっついていくのが見えた。氷の輪郭は次第に成長し、川面は薄氷で被われていった。できあがったばかりの氷の表面には、羽模様のような美しい紋様ができ、月光に反射すると、それは見事な芸術作品だった。
美ヶ原で、目の前の光輝く氷の芸術に舌を巻きながら、夜中の星明りの中で、じっくりじっくりと姿を変えていった水のドラマを想像すると、僕にとっては、一本の枯草さえも愛しく感じられるのだった。近くに一本のカラマツの若木が立っていた。オレンジ色の朝日を浴びて、イルミネーションのように輝いている。吸い寄せられるように側に寄り、何枚かシヤッターを切った。
普段は目にも留まらない木であろう。この瞬間の出会いが嬉しかった。その後、何をどう撮ったのか、夢中で煌きの世界を漂っていた。写真を撮る目的感すら忘れ、極楽の世界に遊んでいるようだった。気がつくと、昼はとっくに過ぎていて集まってきた仲間たちは早朝から飲まず食わずで、全員がフィルムを使い果たしていた。午後になってもまだキラキラしている林道を降りる仲間たちの顔は、言いようのない充足感に溢れたいい顔だった。