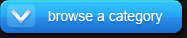足元に潜むアート

10月下旬 長野県下伊那郡売木村 茶臼山高原 「小口さん、写真教室をやってくれないかな。一度、下見に来てよ」という旧知のN氏からの突然の電話が、僕と茶臼山高原との出会いのきっかけだった。 N氏は休暇村茶臼山高原の支配人で、以前、N氏が乗鞍高原の休暇村にいた頃、何かと世話になったので、とりあえず一度、下見に行くことにした。12月の初め、もう里山の木々の葉もすっかり落ちて、初対面の茶臼山(標高1415m)も愛知県の最高峰だと説明されたが、僕の目には殺風景な丘にしか感じられなかった。 N氏と会って、翌年の春に写真教室をやってみることになったのだが、正直に言って自信などまるでなかった。ただ、帰り際に見た茶臼山山頂の素晴らしい星空だけが印象に残った。あれから8年。僕は今ではすっかり茶臼山周辺の自然のファンとなり、事あるごとにその面白さを吹聴して歩いている。 茶臼山高原周辺の自然の面白さを二言で言うならば、「スルメのような」とでも表現したい。北アルプスのような勇壮な自然ではない。一見、どこにでもある...
夕映えのアマダブラム

富士山頂とほぼ同じ高さに建つシャンボチェのパノラマホテルの周囲は、深い谷から湧き上がる濃密なガスに包まれていた。 晴れていればヒマラヤの峰々が夕日に赤く染まる時刻が近づいてはいたが、外は視界ゼロ。ホテルの食堂に座り、諦め気分でチャイ(ミルクティー)を飲んでいた時だった。 ちらちらと気にしながら覗いていた窓の外に、一瞬、白い光が見えた。空の一角に小さな穴が開き、そこから白く輝く山稜がほんの少し見えているではないか。機材を掴み、慌ててホテルのすぐ裏にある展望のよい丘に走った。 この標高ではさすがに酸素が薄く、はぁはぁぜぇぜぇ、心拍数が一気に上がってしまう。焦りながらも素早くカメラをセットしてシヤッターを切り始めた。 大空の穴はみるみるうちに右へ移動し、その中に夕日を浴びたタムセルク(6623m)の見事な双耳峰が顔を出した。オレンジに染まった山肌にヒマラヤ壁の陰影が鮮やかで、それは信じ難いほどの壮絶な美しさだった。夢中で撮り続けていたのは、2~3分のことであったと思う、雲が動き、再びピークがガ...
雨氷の不思議

「無我の境地」という言葉がある。 剣豪や武道の達人が修行の末に辿り着く究極の精神状態などと想像してみるが、写真に置き換えて考えてみると「無我夢中で撮る」という時が、かなりこの境地に近いのではないだろうか。 瓊末なことに囚われず、自然に、のびのびと被写体と一体になって遊ぶ。きっと、こういうときは構図や露出補正といった、普段あれこれと考え悩む問題も気にならず、一心にその美しさ、素晴らしさ、時には不思議さに全身で感動している。この上ない幸福な時だ。忘れられない一日がある。 2004年3月20日。無我夢中で撮り尽くした一日だった。松本フォトアカデミーの仲間たちと美ヶ原に行った時のことだ。メンバーは5人。走り慣れた林道を、まだ暗いうちに登った。前夜までの雨が上がり、冴え冴えと星が輝いていた。やがて東の空か白み始め、昼夜交代のドラマが進行していった。数えきれないほど、このようなシーンに立ち会ってきたが、この日の朝焼けは格別だった。 北アルプス上空のピンク色の帯が次第に下降して稜線に近づく。星の撮影位...
アルプス登擧記

山頂には魔物が棲むとして恐れられていたマッターホルン(4478m)に初登頂したのは、イギリスの挿絵画家エドワード’ウィンパーだった、1865年7月、6年間に渡る8度の挑戦の末、友人と地元ガイドの7人パーティでスイス側のヘルンリ稜から初び頂を米たした。この時、下山途中でザイルが切れ、1人が滑落死する悲劇が起きた。この歴史的登胆の顛末は、ウノノパー自身が挿絵ともに綴った「アルプス登頂記」の中に詳しい。 1976年、僕は北アルプス穂鳥岳の涸沢ヒュッテで働いていた。什事を終え、従業員部屋で懐中電灯を照らして読んだのが、浦松佐美太郎訳、文庫本の「アルプス登単記」たった。まだ見ぬヨーロッパアルプスの名峰・マッターホルンへの夢が、穂高の稜線を越えて広がっていった。マッターホルンに登りたい。その想いは抑え難く、二年後、ヨーロッパアルプスに旅立った。下宿をしたオーストリアのインスブルックで山岳写真協会が主催する登山学校に入り、岩登りを学び、初めて氷河の登り降りも体験した。 その年の夏、手始めにグリンデル...
風と氷のパタゴニア

2006年1月、稀にみる豪宵の日本から盛夏の南米大陸・チリ、アルゼンチンに跨るパタゴニアへ飛んだ。 アメリカのダラスを経由し、赤道を越えてチリの首都・サンティアゴまで約25時間。更に乗り継いで南米大陸の南端、マゼラン海峡に面するプンターアレナスヘ着いた頃には、逆転する季節と12時間の時差が長旅の疲れを増幅してクラクラしていた。 パタゴニアは、かねてから行ってみたい所たった。写真で見た山々の奇怪な岩塔やエメラルド色の氷河湖に迫りだす氷河を、この目で見るのだとの想いが募っていた。 チリ到着の翌日、早速わくわくするシーンが出迎えてくれた。マゼラン海峡沿岸の波打ち際に南極から渡ってきた何百というペンギンたちが営巣し、ひしめいていた。パタゴニアでの撮影は、まず有名なパイネ山群から始めた。エメラルド色のペオエ湖を前景に、氷河が削り作った岩の芸術は、朝夕の光を浴びてドラマチックな光景を演出してくれた。 片道15kmの山道を機材を担ぎ、辿り着いたグレイ氷河の末端では、氷河から吹き出す猛烈な風と対面した。...
常念夕焼け

僕の住む松本の街から、西方やや北寄りに常念岳(標高2857m)は聳えている。 松本平から突然、屏風を立てたように立ち並ぶ北アルプス連峰の中で、最も高く大きく、他を圧しているのがこの常念だ。 ピラミッドのように長く張った稜線の美しさは、日本山岳中、随一ではないだろうか。常念より標高の高い槍ヶ岳や穂高岳は、前山と呼ばれる常念の山並みの背後にあるため、松本や安曇野からは目立たず、やはり里からの主役は常念だ。 僕が常念を撮り始めたのは、もう21年前のことで、母が脳腫瘍で入院し、その付添看護をするため東京から松本へ帰ってきていた頃だった。看護の合間に、自宅近くの城山に続く登山道の中腹から常念を撮った。 ここは、かつてヨーロッパアルプス登山を夢見て、体力作りに駆け登っていた登山道だった。途中、一ヵ所だけ木立が切れて見晴らせる場所がある。それ以来、ここが僕の常念撮影の定点となった。 定点で撮るということは、常念へ向かう方向・角度・距離が限定される。しかし、この足場を限定したことによって得られる幸運なこ...
オリオンと流星

冬になると夜空が澄む。澄んだ夜空に星が鮮やかに輝く。 年を通して、星空か最も美しく魅力的な手節、星空撮影のチャンス到来だ、冬の夜窄を飾る星座たちも、文字通り大スターが登場する、その筆頭は、オリオンであろう、見事な大星座である、その右にV字型をしたおうし座、史に右に少し離れてプレアデス星団(すばる)。オリオンの左下には、全天1の1等星の12倍の明るさを持つ、おおいぬ座のシリウスが輝いている。 この素晴らしい星空を撮影するには、巾街地の明かりを避け、美ヶ原鳥原や高ボッチ高原、乗鞍高原といった高みへ登って行く。 2001年11月18日深夜、標鳥1600mの鳥ボッチ高原へ向かい、車を走らせていた。この夜は、しし座流星群が夜空を乱舞するかもしれないという情報に心を躍らせていた。思い返せばその2年前、1999年にも仲間だちとしし座流星群を撮りに美ヶ原へ登ったことがあった。笑い話だが、その時、時折舞う雪粒が下から登ってくる車のライトに照らされて光るのを流星雨と思い込み、みんなで「スゴイ、スゴイ!」と騒...
一瞬のコントラスト

今も我家から乗鞍岳(標高3026m)がよく見えている、松本巾から眺める乗鞍は、優美なゆったりとした稜線を左右に広げ、とても芙しい。特に冬、澄んだ青空に立つ、真白な雪をまとった乗鞍の姿は、キリリと引き締まり、気品に満ちている。 僕は、乗鞍がたまらなく好きだ。なぜ、という理由を挙げればきりがないと思うが、そんな理由などどうでもよい。とにかく、好きだ。子供の頃から今日まで、数えきれないほど乗鞍へ通ってきた。山頂直下の大雪渓でスキーをし、頂上からも度々、滑り降りた。スキーや山の雑誌の仕事も乗鞍を舞台にやらせてもらった。冬の乗鞍にテントを張って撮影した時は大雪に遭い、命懸けで山を下った。 第一冊目の写真集「太陽の背なか」のメインフォトは、美ヶ原から撮った真紅な夕焼け空に立つシルエットの乗鞍たった。第二冊目の写真集「水の回廊」で、最も作品の多かっだのが乗鞍たった。現在、写真教室で最も頻繁に通っているのが乗鞍だ。以上、箇条書きに、僕と乗鞍の関わりを書いてみた。やはり、乗鞍とは相当な因縁があるのだ。 忘...
稜線の彼方に

長男が生まれた翌日、雪の美ヶ原高原に登った。 18年前の初冬のことだ。真白に雪化粧した北アルプス、槍穂高連峰が目の前に聳えていた。朝日に山々が赤く染められるモルゲンロートを撮りながら、誕生した息子の名前を「稜」にしようと、その時、決めた。 松本に生まれ育った僕が、故郷の山々を意識したのはいつのことだったか。地元の高校への自転車通学の途中で仰ぎ見た冬の常念岳に、圧倒的な存在感を感じたのが最初であったように思う。故郷の山々を撮るようになって、自分の生まれ育ったこの地が類稀な自然美に恵まれていることを知った。 山と対峙し、シヤッターを切るごとに、僕の山への想いは素晴らしさから有難さに変わっていった。そして、山と向き合って生きられることが、心の底から幸せだと思えるようになった。写真を撮るという行為は、被写体をただ見るだけではなく「見つめる」ということなのだが、僕にとって山々はその対象として比類のないものとなった。故郷の山々は「見つめ続ける」特別で大切なものだ。 一例を挙げれば常念岳(2857m)...
アルプスのエーデルワイス

キッシュタインホルン・3203m。頂上直下の氷河まで、山麓のカプルーンという小さな村からゴンドラがかかっている。山頂駅の展望台から、オーストリア・アルプスの最高峰を眺めてから、中間駅までゴンドラで降り、ここからトレッキングをスタートした。 8月、残雪の残る緑の山腹をトラバース気味に下っていると、突然、身体が青空の中に放り出されたような開放感に包まれた。両側が切れ落ちた草付きの尾根に出たのだ。 山頂を背に、さらにはるか眼下の湖に向かって下る途中、色とりどりのアルプスの花々に目を奪われて写真を撮っていると、牧童らしきおじさんが登ってきた。被っているチロリアンハットに本物のエーデルワイスが3輪挿してあるではないか。ドキドキしながら「それはどうしたの?」と聞くと「この下に咲いているよ」と日焼けした笑顔で教えてくれた。 そこは登山道から外れた、片側がスパッと切れ落ちた岩壁の上だった。 「あった!」白いエーデルワイスが本当に咲いていた。 周囲にいくつか咲いているが、近寄れそうな株はひとつだけだ。落ち...
ふたひらの桜

今年もまた、日本列島を桜前線が北上している。その最中、記録的な豪雪だった今冬の最後の寒波が精一杯の抵抗を示して、北信濃は春の雪に見舞われた。 ザゼンソウが顔を出し始めた湿原の一面の雪景色の中を歩いていると、まだまだ春は遠く感じられる。東京では桜満開が伝えられる頃、信州の山では木々に霧氷が降り、山の湖に薄氷が張る。しかし、日一日と強さを増す日射しは確実に氷を溶かし、木々の芽を膨らませる。行きつ戻りつ季節は振動しながら、やがて押し寄せる桜前線に飲み込まれ、信州は春一色となる。 桜に寄せる日本人の心は古より育まれ、命に刷り込まれた独特なものであると思う。とりわけ雪深く、厳しい冬を暮らす者たちにとって、桜は単に春の花ではなく、格別な存在に違いない。それは待ちわびる暖かな春の象徴であり、命の躍動である。一斉に咲き誇る桜に、人々は確かな力強い命の息吹を感じ、それを寿ぐのだ。 桜は開花からほぼ一週間で満開となり、2~3日後には散り始める。「せっかく咲いたのに、ああ、もったいない」と心でつぶやきながら、...
一輪のヒマワリ

「何なんだ、今のは?」時速120kmmで走る車のハンドルを握る僕の視界の右側を、黄色い何物かが掠めて過ぎた。 停まろうか、それとも走り過ぎようか迷っている時間はなかった。バックミラーを反射的に見る。幸い後続の車はない。思い切って車を停め、その「黄色」が何物かを見極めるために70mほどレンタカーをバックさせた。 今、思い起こせば、冷や汗ものの無謀な行為だった。もし、ポリスにでも見つかっていたら、こってりと絞られ、罰金を払う破目になっていたに違いない。なぜならそこは、フランスの高速道路上だったのだから。 パリの街を出て、高速道路を南下し、オルレアンを通り、美しい古城で知られるロワール河沿いの地方を通り抜けて、一路、南フランスへ向かって車を走らせていた。やがてめぐり会う地中海の鮮やかなブルーを想うと心が踊った。ワインで有名なボルドーの街を過ぎて道路は一直線に地中海に延びていた。辺り一面は行けども見渡すばかりの長閑な農村風景が広がっていて、信州育ちの僕には少々退屈に感じられた。 そんなときだった...